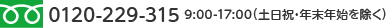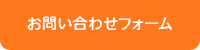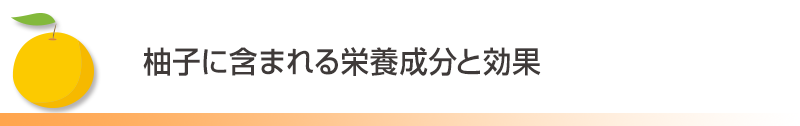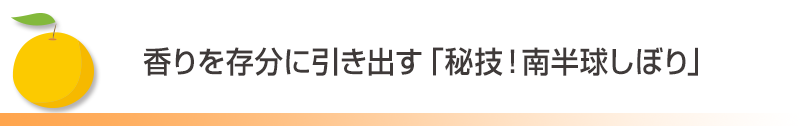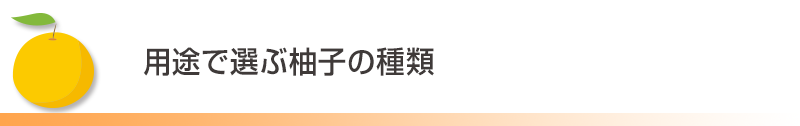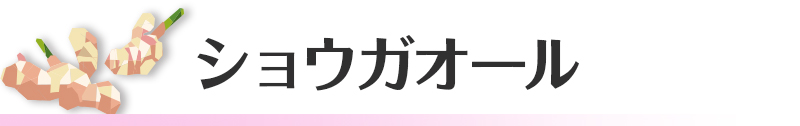春から初夏が旬のアスパラガス。今回は種類、栄養、保管のコツなどをご紹介いたします。

根を植えてから2週間で芽が出てきたところです
アスパラガスの種類いろいろ
グリーンアスパラガス
 太くて短いものが柔らかいといわれ、穂先が固く締まってピンとしているものが新鮮です。また緑色が濃いものの方が一般的に栄養価に優れているといわれています。
太くて短いものが柔らかいといわれ、穂先が固く締まってピンとしているものが新鮮です。また緑色が濃いものの方が一般的に栄養価に優れているといわれています。
新鮮ならば生でも食べることができ、独特の甘みとほのかな苦みが楽しめます。
ホワイトアスパラガス
グリーンと同じ品種なのですが、太陽の光に当てないよう土をかけて軟白栽培します。栽培に手間がかかる分、値段も若干お高めですが柔らかい食感が楽しめます。
紫アスパラガス

抗酸化作用のある紫色の色素成分“アントシアニン”が多い品種です。加熱すると紫色が抜けてグリーンになってしまうため、生食がおすすめです。
アスパラガスの栄養素
 アスパラガスから発見された栄養成分であるアスパラギン酸は、エネルギーを作り出すときに利用されるアミノ酸で、新陳代謝を活発にして疲労を和らげる効果があります。よく栄養ドリンクにもよく配合されています。
アスパラガスから発見された栄養成分であるアスパラギン酸は、エネルギーを作り出すときに利用されるアミノ酸で、新陳代謝を活発にして疲労を和らげる効果があります。よく栄養ドリンクにもよく配合されています。
また穂先にはルチンという成分が含まれており、血管を丈夫にする働きがあります。
このほかにも妊婦さんに必須の栄養素である葉酸やビタミンKなども含まれています。

アスパラガスの花です
美味しく食べる保存のコツ
買ってきたらすぐに茹でて冷蔵庫保管
アスパラガスは鮮度が命。特にホワイトは傷みやすいのですぐに食べないのであれば生のまま放っておくよりも、さっと茹でてから冷蔵庫で保管する方が風味は良いといわれています。
生で保存する場合には立てて冷蔵庫保存
アスパラガスを横にすると、立ち上がろうと無駄なエネルギーを使うことになり鮮度が失われてしまいます。そこで生育している時と同じように立てた状態で保管することがおすすめです。その際には濡らしたペーパータオルで切り口部分を覆い、ビニール袋に入れることもお忘れなく。
この春、我が家ではアスパラガス栽培に初挑戦しています。根を植えつけるとその年は根を太らせるために収穫を控えるのですが、翌年からは本格的に収穫が可能となります。それ以降10年以上も同じ根から収穫ができるのでコスパの良さに魅力を感じ、今から来年が楽しみです。
ミリオン管理栄養士 大森貴舟