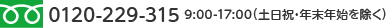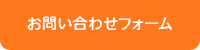冬の味覚「柚子」のおはなし

どこか温かみのある香りの「柚子」は、冬の汁物やお正月料理に欠かすことのできない食材です。
冬至に柚子湯に入れば邪気が払われ、一年間風邪をひかないという言い伝えがあり、今でも多くの日本人に親しまれています。
我が家では12月に入ると家族総出で収穫をはじめます。柚子はその可愛い見た目とは異なり、枝にはとても鋭い棘(トゲ)があって、地面に落ちた棘をうっかり踏むとスニーカーの靴底をも貫通させるほどです。そんな厄介な柑橘であっても広く人気なのは、日本人の心をほっこり温める香り高き果実だからではないでしょうか。

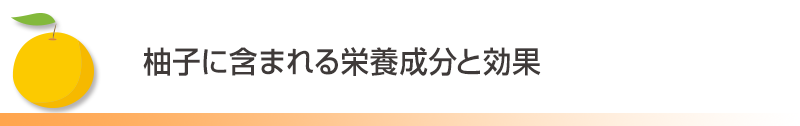
柚子にはビタミン類や香気成分が多く含まれ、それらには様々な健康効果が報告されています。その中で代表的なものをいくつか挙げてみました。
抗酸化作用
柚子にはビタミンC、β-カロテン、ヘスペリジン(ビタミンP)などが豊富に含まれています。これらはストレス、紫外線、喫煙、激しい運動などによって生じた有害な活性酸素を除去し、病気や老化から身を守ってくれます。
感染症予防効果
βカロテンには粘膜を丈夫にし、免疫力を高める働きがあります。またビタミンCには白血球の働きを高める働きがあり、へスペリジンにはビタミンCの吸収を促進する働きがあるなど、各成分が連携して働いています。
美肌効果
シミ、そばかすの原因であるメラニン色素は、チロシンというアミノ酸から作られます。このチロシンを増やさないよう、ビタミンCが防いでくれます。
またヘスペリジンにはお肌の構成成分であるコラーゲンの合成促進作用があります。
血流改善効果
白いワタの部分に多く含まれるヘスペリジンには、血管を丈夫にし、手足の末端にある毛細血管を広げて血流を良くする効果があります。ワタの部分は捨ててしまいがちですが、マーマレードのようにすれば摂取しやすくなります。
疲労回復効果
果汁にはクエン酸やリンゴ酸などの有機酸が豊富に含まれます。これらは疲労物質である乳酸を分解してエネルギーに変える働きがあり、疲労回復効果があります。
リラックス効果
柑橘系に含まれるリモネンなどの香気成分は、爽やかな香りを持ち、脳を刺激してストレスを緩和する働きがあります。アロマテラピーでは、柑橘系の香りは気持ちを明るくし、不安な気持ちを和らげてくれるといわれているようです。

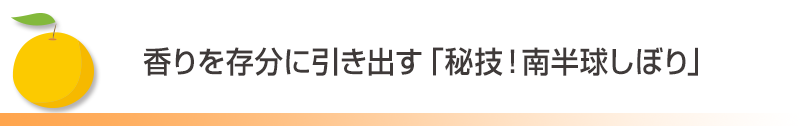
さて柑橘の香気成分にはリラックス効果があるとお話しました。中でも柚子独特の香りをもたらす「ユズノン」という香気成分は、果実1個にわずか100万分の1グラムしか含まれない希少成分です。この成分は、果皮にある油胞というカプセルの中に多く存在するため、カプセルを潰すように絞ることが香りを十分に引き出すポイントといえます。そこでユズノンを十分に引き出す絞り方「南半球しぼり」をご紹介いたします。
「南半球しぼり」とは
柚子を真横に2つに切り、切った断面を上にして、反対側の皮の方を下にします(ちょうど南半球だけのように見えますよね)。
そのまま、皮の方から果汁絞り器でグリグリと潰せば、ユズノンが空気中に飛び散ることが少なくなり、果汁の中に溶け込んで香りをホールドできるのです。

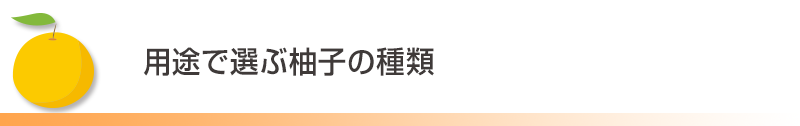
柚子にはいくつか種類がありますが、これらの種類がよく出回っているようです。
本柚子
本柚子は、小~中くらいの大きさで、どんな料理にも使いやすい柚子です。果汁は少な目ですが香りは良く、中身をくり抜いて柚子釜にも利用できる重宝な柚子です。どれを買おうか迷ったらまずは本柚子をおすすめします。
花柚子
花柚子は一才柚子とも呼ばれ、本柚子に比べて小ぶりです。果汁が多く、皮も薄いので果汁を利用したい時に選ぶとよいでしょう。また種が少な目なので、柚子湯にも使いやすいでしょう。
獅子柚子
獅子柚子は、果皮が非常に厚くてボコボコした巨大な柚子です。生食には向きませんが、中身は取り除き、皮をマーマレードに利用すると美味しく食べられます。

—————————————————————————–
今回は日本の冬に欠かせない「柚子」についてあれこれお話しました。
旬の食材は美味しさと必要な栄養を与えてくれます。ぜひとも活用していただけたらと思います。
執筆:管理栄養士 大森貴舟
2019年12月6日 1:51 PM | カテゴリー: 未分類