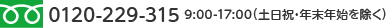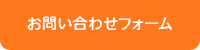ロシア料理を代表するスープ「ボルシチ」でお馴染みの野菜・レッドビーツ。日本名を「火焔菜(かえんさい)」と呼ぶ鮮やかな赤色が特徴のこの野菜は「奇跡の野菜」とも言われるほど栄養価が高く、世界では注目されている野菜です。
その理由の一つがNO(エヌオー)という一酸化窒素を豊富に含んでいること。NOは血管の筋肉を柔らかくして血流をスムーズにする働きがあると言われ、このことを発見したルイス・イグナロ博士は1998年にノーベル賞を受賞し注目度が高まりました。
その他にもオリゴ糖や食物繊維、強い抗酸化力のあるベタシアニンなど、美容や健康に嬉しい成分に恵まれています。
とはいえ日本ではまだ馴染みが薄いため、店頭ではあまり見かけることがありません。既製品のジュースなど生活に取り入れやすい形で摂取するのがおすすめです。