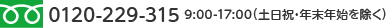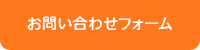「おせち料理」で開運はいかがですか
お正月に欠かせない「おせち料理」は、年神様に一年の無事と幸福を願ってお供えする特別な料理です。それを下げて我々もいただくことで、御利益にあずかれるといわれます。
さて、おせちに用いられる食材には数多くの縁起の良い意味と願いが込められています。ただの風習とせず、おせちに込められた意味を想いながら味わえば、めでたさも一段と増し開運につながるのではないでしょうか。
おせち料理は重箱に納められますが、これは「めでたさが重なるように」という意味が込められています。縁起の良い奇数の三段重にもう一段重ねた与段重か、もしくは与段重にもう一段重ねた五段重が正統といわれています。
また、各段には納められる料理が決まっています。
黒豆、数の子、田作り、栗きんとん、かまぼこ、伊達巻、たたきごぼう、昆布巻き など
鯛やブリなどの焼き魚、海老などの海の幸
紅白なます、なまこ酢、酢蓮根、菊花蕪 など
蓮根、里芋、クワイ、ごぼう、八ツ頭 などの煮物
神様から頂いた福を詰める場所として空にしておく
※地方によって若干異なります
重箱は神様への敬意を表すために用いますが、最近では一段重のコンパクトなおせちが主流のようですし、生活スタイルに合わせて臨機応変にアレンジしてもよいかもしれません。もし重箱がない場合には丸いお皿に盛りつけてはいかがでしょうか。丸いお皿は角がないので「すべてが丸くいく」といわれ、縁起ものに使われます。
 黒豆
黒豆
「マメに働けるように」との健康長寿の意味が込められている。
黒い皮には抗酸化作用の強いプロアントシアニジンが豊富に含まれている。
 数の子
数の子
数の子はニシンの卵。子孫繁栄を意味する。
魚卵の中ではコレステロールやプリン体が低く、DHAやEPAは多く含まれている。
 田作り(ごまめ)
田作り(ごまめ)
田作りは、いわしの幼魚の佃煮。小魚を畑にまいて肥料にしたことから五穀豊穣を意味する。
小魚は小骨も食べることができ、カルシウムの補給に良い。
 栗きんとん
栗きんとん
黄金色は金運上昇を意味する。また干して保存食に用いる搗栗(かちぐり)から「勝負に勝つ」という意味も込められている。
 紅白かまぼこ・紅白なます
紅白かまぼこ・紅白なます
赤は厄除け、白は清浄を意味し、紅白が揃ったとき、めでたさを呼ぶとされている。かまぼこは日の出を表している。
 伊達巻
伊達巻
形が巻物を表すことから、学業成就や仕事の大成を意味する。
 昆布巻き
昆布巻き
昆布は「養老昆布(よろこぶ)」や「子生(こぶ)」とも書けることから、不老長寿や子孫繁栄を意味する。
カルシウム、食物繊維、ヨウ素などが多い。
 鯛・鰤の焼き物
鯛・鰤の焼き物
鯛は「めで鯛(たい)」として恵比寿様が持つ祝い魚、鰤は出世魚。DHAやEPAが多い。
 エビの焼き物
エビの焼き物
「長いひげと腰が曲がるまで健康長寿に」との意味。
カルシウムやビタミンEが多い。
 なまこ酢
なまこ酢
俵の形に似ていることから豊作を意味している。
アミノ酸、コンドロイチンやタウリンが多い。
 根菜系の煮物
根菜系の煮物
数種の野菜を一緒に煮こむので家族円満を意味し、蓮根は穴があることから「先が見通せる」、ゴボウは「まっすぐ育つ」、里芋は子芋がたくさんついているため子孫繁栄、くわいは大きな芽が出るため出世の意味がある。
おせち以外にもお飾りや作法などいろいろとあるようですが、食に関わるものをいくつかご紹介します。
![]() 若水:元旦に初めて汲む水を「若水」といい、その水には邪気を払ってくれるといわれています。この水を使ってお雑煮などを作ります。
若水:元旦に初めて汲む水を「若水」といい、その水には邪気を払ってくれるといわれています。この水を使ってお雑煮などを作ります。
![]() 雑煮:おせち料理と同様に年神様にお供えした餅を食べるので、年神様のご利益をいただくことができるといわれています。お餅は長く伸びることから長寿の意味が込められ縁起の良い食べ物です。
雑煮:おせち料理と同様に年神様にお供えした餅を食べるので、年神様のご利益をいただくことができるといわれています。お餅は長く伸びることから長寿の意味が込められ縁起の良い食べ物です。
![]() 祝い箸:両端が細くなっている箸で両口箸とも呼ばれ、一方は年神様が、もう片方は私たちが使えるよう、このような形になっています。神様と共に使うことでより多くのご利益をいただけることでしょう。ただし両方使えるからといって、ひっくり返して使うのはタブーです。
祝い箸:両端が細くなっている箸で両口箸とも呼ばれ、一方は年神様が、もう片方は私たちが使えるよう、このような形になっています。神様と共に使うことでより多くのご利益をいただけることでしょう。ただし両方使えるからといって、ひっくり返して使うのはタブーです。
![]() お屠蘇:「屠蘇」とは「邪気を屠(ほふ)り魂を蘇らせる」という意味があり、邪気を払い、無病息災、長寿を願って飲む薬酒です。
お屠蘇:「屠蘇」とは「邪気を屠(ほふ)り魂を蘇らせる」という意味があり、邪気を払い、無病息災、長寿を願って飲む薬酒です。
ご家族団らん、おせちの豆知識を語りながら、楽しいお正月を過ごしてはいかがでしょうか。今年一年が皆様にとって良い年となりますようお祈り申し上げます。
管理栄養士:大森貴舟
2019年12月22日 3:54 PM | カテゴリー: 健康寿命を延ばすために