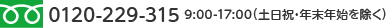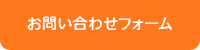秋から気をつけたい感染症と予防法
ウイルスが活発化し始める季節
秋から冬にかけての季節は、感染症が流行り始める時期です。
気温が低くなり乾燥すると、感染症の原因となるウイルスや細菌が活発に活動をはじめます。また夏の暑さで弱っているところに、気温が下がって免疫力が低下すると、感染症リスクが高まります。
冬はさらに猛威を振るうため、その前段階の予防が大切なのです。
特に気をつけたい高齢者の感染症
高齢者になると若い人に比べて免疫機能が低下します。これはウイルスのような外敵から防御する免疫細胞(特にTリンパ球)の数が低下することによるもので、さらにカラダの中で過剰な炎症反応を起こしやすくなり、肺炎などの病状を長引かせたり重症化させたりします。
高齢者がかかりやすい感染症には、以下のようなものが挙げられます。
—–【感染性胃腸炎】—–
細菌やウイルスに感染すると、嘔吐や下痢などを起こすのが特徴です。11月頃から感染者が増え始め、12月をピークに一旦減少しますが、1~3月に再び増える傾向があります。
12月のピークには子供から大人までが感染するノロウイルスが多く、1~3月には小児が感染しやすいロタウイルスが増えます。
ノロウイルスは、2~3日程度の激しい嘔吐と下痢が続くことが特徴で、ウイルスに汚染された食品(主に魚介類)を加熱せずに食べたり、感染者の嘔吐物や便から飛び散ったウイルス(飛沫感染)を吸い込むなどで感染します。
ワクチンや予防薬がないため、十分な加熱調理を行うことや、調理器具の消毒、手洗いなどが重要となります。感染者が近くにいる場合は、使い捨てのマスクや手袋を着用し、消毒しながら二次感染を防ぐようにしてください。
—–【インフルエンザ】—–
インフルエンザウイルスに感染すると、通常1~3日後に発症し38℃以上の高熱、鼻水、のどの痛み、咳、頭痛,関節痛,筋肉痛などが現れます。しかし高齢者の中には高熱が出ない場合もあり、インフルエンザだと気がついた頃には症状がさらに進行していることがあります。免疫力の落ちている高齢者には命にかかわることもあるため、予防がとても重要です。
感染経路は、インフルエンザに感染した人の咳やくしゃみといった飛沫で二次感染を起こします。予防にはワクチン接種、手洗い・うがい、マスク、保温・保湿などを心掛け、不調を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。検査キットを用いれば15分程度で結果がわかります。万一、感染してしまったら発症後48時間以内のまだウイルスがあまり増殖していない時期に投薬を開始する事が早期回復には大切です。
———-【肺炎】———–
肺炎は、細菌やウイルスなどが肺に侵入することによって発症します。インフルエンザウイルスによる空気感染の他、健康な時には問題にならないような口中の菌や、外界に広く存在している低毒性の菌であっても、免疫力が低下していると、肺の内部に炎症を起こしやすくなります。症状は、高熱、咳、胸痛、痰などが特徴的です。しかし高齢者は高熱が出ないことがあり、気づくのが遅れないよう注意が必要です。肺炎は通年見られますが、特に11~3月には他の感染症と併発して増えます。
予防法としては、肺炎球菌予防接種、口腔を清潔に保つ、手洗い・うがい、マスク、保温・保湿が大切です。
免疫力が落ちた高齢者は、完治に時間を要します。また命にかかわる病気を併発する可能性も十分に考えられるため楽観視せず、感染症の予防に努めていきましょう。
執筆:管理栄養士 大森貴舟
2019年10月25日 3:19 PM | カテゴリー: 健康寿命を延ばすために