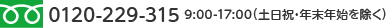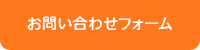花粉症の季節が到来!
花粉症の症状といえば、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどがあります。
特に春先はスギやヒノキの花粉が多く飛ぶ時期でもあり、これらの症状が急増する季節でもあります。
今回は発症の原因、メカニズム、そして予防方法と緩和対策についてご紹介したいと思います。
症状を引き起こす花粉は現在50種類以上報告されており、花粉症患者の約7割はスギ花粉が原因と推測されています。これは日本が戦後復興のため、スギの植林を進めた弊害ともいわれています。
しかし他にも原因となる花粉は一年中飛散しており、下図のように初夏にはホソムギやカモガヤなど、秋にはブタクサやセイタカアワダチソウなどが飛散のピークを迎えます。スギ花粉しか発症しない人もいれば、複数の花粉に発症する人もいるため、自分がどの花粉に影響を受けやすいのかを見極め、その季節に向けて対策することが大切です。
さて花粉はとても小さな物質で、例えばスギ花粉は直径30マイクロメートル(1マイクロメートル=1ミリの1000分の1)しかありません。
こんな小さな花粉なのになぜこんなにも悪さをするのでしょうか?
じつは花粉にはアレルギーを引き起こすタンパク質が含まれており、これが原因となっています。もう少し詳しく説明すると、花粉のたんぱく質が鼻粘膜に溶け出すと、それを異物として認知し、排除しようと働きます。加えて、二度目以降の侵入時に備えて抗体を作って待ち構えるのですが、この抗体が過剰に働いた時、じつに迷惑な炎症物質(ヒスタミンなど)を大量発生させてしまいます。そして炎症物質は鼻腔を腫らし、鼻づまりにさせたり、その刺激でくしゃみや鼻水が出るというわけなのです。
花粉に触れない服装
花粉症の人はもちろんですが、そうでない人も今後の発症を予防するためになるべく花粉に触れないことが大切です。例えばメガネ、マスク、帽子を被り、表面がツルっとして花粉が付着しにくい生地の服を着ることは有効です。
また帰宅の際には玄関に入る前に花粉を必ず払い、うがいや顔を洗うことも大切です。

ストレスをためない・睡眠を取る
免疫機能を正常に保つにはストレスをためない、充分な睡眠を取るなどの正しい生活習慣を心がけましょう。また飲酒やタバコを控える事も鼻の粘膜を正常に保つために重要です。
健康食品・健康茶で予防を
そもそも、花粉症は過剰な免疫抗体反応が引き起こす症状です。したがって免疫抗体反応を調整してくれる効果の乳酸菌や乳酸菌生産物質を選んで毎日摂取することで予防となります。また炎症を鎮めてくれる働きのあるお茶(甜茶、べにふうき茶などがおすすめ)を摂取するのもよいでしょう。これらは症状が出てから摂取するより、その前から摂取しておくことでより効果を発揮してくれます。

早めはやめの受診を
もし症状が現れた場合には、早めの受診をおすすめします。症状がごく初期は、鼻粘膜の炎症は進んでいないため、早く正常化させ、重症化を防ぐことができます。症状緩和には抗ヒスタミン薬が処方されたり、鼻スプレー(局所ステロイドスプレー)、レーザー治療などが行われています。
ミリオン管理栄養士 大森貴舟
2020年3月18日 1:23 PM | カテゴリー: 健康寿命を延ばすために